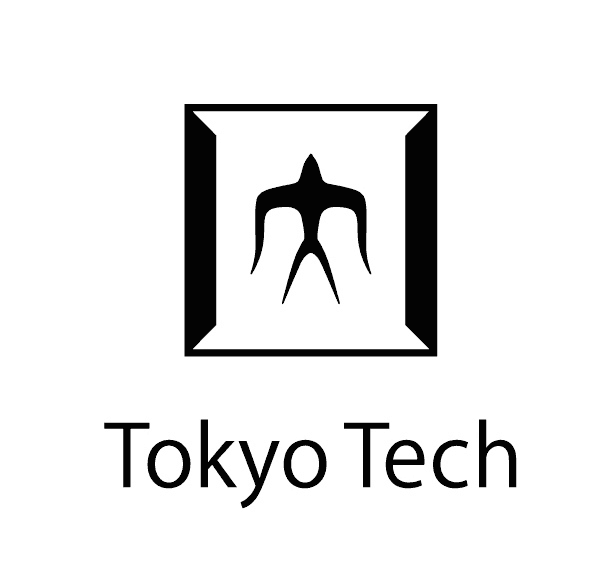
東京工業大学 黒澤研究室
音響機器の新たな音質劣化要因の実証と試聴実験による検証
1 研究の概要
オーディオ機器の再生音質は,現在計測されている特性から,音質の良し悪しを評価することは不可能である。現在の計測データが十分な特性であっても,音質は大きく異なることは広く知られているが,どのような現象,どのような計測に依り,音質の差異が発生しているかを知ることはできていない。そこで本研究では,未知の信号ひずみを明らかにし,音響機器の音質劣化原意を明らかにすることで,高音質化の道筋を明らかにしていくことを試みた。その結果,これまで計測されていなかった強い非線形現象によるひずみ波形の存在を指摘し,音質への影響を検討した。また,音質の評価方法についても検討を行い,瞬時切替の比較試聴実験を通し,音質劣化を有無を明らかにする試聴実験方法を検討している。
2 研究の目的と背景
オーディオ業界では,いわゆるハイエンドオーディオの音は,一般的なオーディオ装置に比べて,原音に近い音を再生できるが,何故なのかは何十年ものあいだ未知の問題として残されてきた。本研究では,音質を決定づけている要因について検討し,合理的な高音質化の手法を明らかにすることを目的としている。
ここに,周波数特性,出力パワー,高調波ひずみ率特性がほぼ同等の装置があったとして,それらの音質や再生される音楽の聴感的な傾向が同じであるかというと,まったく異なる音質となる場合がほとんどである。この現実に対して,背景にある物理現象と,その物理現象の測定による定量化を実現する必要がある。この技術が開発されれば,音響機器の音質は驚くほど向上し,手頃な価格で,現在のハイエンドオーディオより一層高音質な音で音楽を楽しむことが可能となる。本研究はそれを実現しようとする試みである。
3 研究内容
(1) 音響機器の新たな音質劣化要因の実証と試聴実験による検証
① 強い非線形作用によるひずみの検出と波形再生に関する研究
抵抗器,キャパシタ,ケーブルなどの受動部品により,音響機器の音質が変化することを,計測を通して明らかにすることを試みた。その結果,独自の計測手法により,これまで知られていない強い非線形作用によるひずみ波形の存在を明らかにした。


② スピーカーの歪み波形解析に関する研究
電子機器で発生した強い非線形ひずみが,スピーカーから再生される音の波形にどう影響しているかを計測に依り明らかにすることを試みた。マイクロホンで取り込んだ音波形を解析した結果,電子機器での波形ひずみ影響が出ていることが一般化調和解析の結果分かった。


③ 試聴実験による強い非線形による波形歪みが音質に与える影響の検証
受動素子で生ずる強い非線形性に起因する波形ひずみが,音質の変化に与える影響を主観的な音質評価にどう影響するか,比較試聴実験により検証した。DA変換器以降のアナログ回路を用いて,同一の回路構成をした2台の音響機器で,オリジナル回路から一方の回路受動部品を入れ替えることで,音質への影響を調査した。試聴実験の結果,ひずみを減らした回路の音質は必ずしも好まれず,各個人が普段聴いている音質との比較により好ましい方を選ぶ傾向が強いことが分かった。このことから,音質への影響を主観評価に依り検証するためには,回路の有無による音質変化の有り無しで行うのが妥当であることが分かった。


4 本研究が実社会にどう活かされるか―展望
音響機器ごとに固有の音質を与えている未知のひずみを理解することにより,これまでにない高音質な音響システムを実現することができる。これまでの電気音響システムでは,その再生音がひどく歪んでいるのにも拘わらず,そのひずみはほとんど認識されてこなかった。しかし,ひずみの存在とその影響を明らかにしつつある本研究により,ひずみの実態が広く理解され,ひずみの無いシステム構築へと向かうことができる。
高音質な音響システムは,臨場感のある仮想空間を作り出すのは必須の要素である。また,音楽を真に楽しむためには,生の演奏により近いレベルでの高音質化が必要である。こういった高音質は,日常的に溢れる音,例えばテレビの音,映画の音,公共空間での案内放送,機械と人がコミュニケーションするための音(例えばセルフレジの音声など),すべてに渡り人の生活を快適なものとする。音がいいことは,音が良くなって初めて気が付くので,現状気にする人は多くは無いが,いい音が広く行き渡ることで,高音質化がもたらす心地よさは初めて認識されることとなろう。
かつて,うるさいエアコンがなんの抵抗も無く受け入れられていたが,40年ほど前に静粛工学という分野が注目されるようになっていこう,生活の中での騒音が飛躍的に改善された。いまどき動作音の出るエアコンは人々の生活に受け入れられない。同様のことが電気音響システムの音質の世界でも起きることを予期している。
5 教歴・研究歴の流れにおける今回研究の位置づけ
最初の取り組んだ研究は,音響振動を用いたアクチュエータの研究に関するもので,音と物との間の相互作用により動きを伝えるデバイスについてであった。その中で,電気電子工学,機械工学,材料工学に関する分野での取り組みをしてきた。電気音響の分野においても,主に電気電子工学,機械工学,材料工学が大きな影響をもち,ともに音響工学の一分野をなしている。
今回の研究は,音と人の間に入る音響システムに関する研究で,情報工学とも関連してくる。したがって,これまでの研究領域の基礎となる部分は同じで,結果が人と関連してくるところで面白みの増した研究領域となっている。元々一番興味のある分野であることから,これまでの研究歴がフルに役立つ研究となると考えている。
6 本研究にかかわる知財・発表論文等
知財
現在準備中
発表論文
庄司晃太,黒澤実, “アルミ電解キャパシタで生じる高調波ひずみと電圧・電流・周波数の関係についての検討” 日音講論集 pp. 433-434,Sept. 2023.
7 補助事業に係る成果物
(1)補助事業により作成したもの
該当なし
(2)(1)以外で当事業において作成したもの
該当なし
8 事業内容についての問い合わせ先
所属機関名: 東京工業大学工学院(トウキョウコウギョウダイガクコウガクイン)
住所: 〒226-8501
神奈川県横浜市緑区長津田町4259
担当者: 准教授 黒澤実(クロサワミノル)
担当部署: 電気電子系(デンキデンシケイ)
E-mail: mkur@ee.e.titech.ac.jp
URL: http://www.kurosawa.ip.titech.ac.jp